はじめまして。徳島大学 人と地域共創センターの教員で、高齢化問題意識啓発グループ代表の鈴木尚子と申します。
専門は教育学(社会教育・生涯学習領域)で、大学では公開講座の企画運営や地域貢献事業に携わっていることから、様々な年代の、異なる経歴を持った人びとの学びを支えるための研究や実践活動をしています。

近頃、地域の至る所で、認知症が疑われる高齢者のかたを見かけることはないでしょうか。私自身の職場でも、十数年前からそうした人びとの学習支援に携わる機会がある中で、徐々に大変さを実感してまいりました。しかし、もともとの専門性からだけでは対応に限界を感じ、最初は自身が認知症を(医学・看護学・健康科学の蓄積を中心に)正確に知ることに努め、関連した学会にも入会し、本格的に学び始めました。現在は、国民の認知症への理解促進や、地域における認知症の人やその家族介護者の学習のあり方に関心を寄せ、研究を続けています。
この過程で、自身が開講した公開講座において、地域で認知症に対して何ができるか話し合う機会を設けるとともに、賛同してくださる有志市民とともに、高齢化問題意識啓発グループを結成しました。その後、かれらとともに高齢化や認知症に関して市民の意識を高めるための諸活動を考案し、現在徳島県内各地で実施しています。こうした経験をもとに、このたび認知症について分かりやすく伝える絵本のストーリーを作成し、出版しようと思い立ちました。
「認知症になっても、住み慣れた地域で安心して暮らせる社会をつくりたい」
そのためには、自身の専門性から何ができるだろうか、という思いから、このプロジェクトを立ち上げました。
この絵本(『にんちしょうって、なんだろう?』、全30頁)は、認知症の症状のいくつかとその時の本人の気持ちに加え、周囲の人の適切な接し方について、子どもの目線に立ち、日常の風景とともにやさしい言葉で伝えています。幼い子ども(5歳程度)から大人まで誰でも理解しやすい内容にしましたので、個人的なご利用の他、家族介護者の支援、教育・医療・介護施設等での啓発ツールとしても活用できると思われます。
この絵本制作と出版、そしてその活用を通じて支え合いの輪を広げ、「認知症にやさしい地域づくり」(注1)を目指します。また、その基盤となる調査研究を通じて学術上も貢献してまいります。ぜひ、この活動にご賛同いただき、ご支援をお願いいたします。
進む超高齢社会と認知症をめぐる課題
日本では、数十年前から急速なスピードで高齢化が進行しており、近年の研究では2022年時点において、認知症の人及び軽度認知障がいの人を合わせると、65歳以上の27.8%を占めることが報告されています (注2)。特に徳島県は全国に先駆けて高齢化が進展しており(図1)、認知症を起因とする諸問題は、医療・介護分野だけでなく、地域社会のあらゆる分野に影響を与えています(注3)。

図1 徳島県及び全国の高齢化率と徳島県人口の年齢3区分別推移
2024年1月より、「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が施行され、認知症への正しい知識や正しい理解を深めることが謳われています。しかし、認知症という言葉は聞いたことがあっても、それが何を意味しているのか、十分に知らない人も少なくありません。認知症の本人も初期には困惑していますが、その家族もどこに相談していいか分からず孤立し、「介護離職」に至るケースも増えています。また、若者が少ない徳島県等の地方では、「老老介護」の高齢者や単身世帯の認知症の人もいらっしゃいます。また、日本には「恥の文化」があり、家族や親族に認知症の人がいても「隠したがる」傾向があることも、うかがい知る機会がありました。
こうした問題を解決していくには、認知症に対する社会全体の理解を効果的に高め、支え合いの輪を広げることが不可欠です。
「認知症にやさしい地域づくり」のために、今一人ひとりができること
認知症になっても、住み慣れた地域で安心して暮らせる地域を作っていくために、今、私たちに何ができるのでしょうか。
高齢化の進行により、医療機関の受診者数や介護施設・在宅医療サービスの利用者は今後さらに増加し、医療・介護従事者の安定した確保が困難になる状況が見込まれています。また、認知症の社会的経費が甚大であることも指摘されており(注4)、これが国家としての財政を今後いっそう圧迫していくことが予測されています。こうした中、地域に生きる一人ひとりの住民が、たとえ地縁・血縁関係がなくとも支え合える関係性を築くことが、長期的に見れば膨張する社会保障費の抑制にもつながり、持続可能な社会を築く上での助けになります。
認知症の様々な症状は、周囲の人がどのように接するか、ということが大きく影響します。ちょっとした接し方の違いで、それまで戸惑いの表情を見せていた認知症の人がホッとすることがあるのです。私たち一人ひとりが認知症を正しく知り、適切な接し方を身につけ、見知らぬ人同士であっても助け合えることができれば、認知症になっても医療・介護施設にできるだけ頼らず、少しでも長く住み慣れた地域で暮らせることにつながります。どうしても最初は自分ごととしての「予防」に関心が向きがちですが、それ以外にも、「地域社会に対して自分もできることがある」と知るための重要な入り口に、このプロジェクトは位置づけられます。

私の挑戦:教育学の蓄積を認知症の啓発活動に活かし、効果的に実践力を身につける
私は教育学を主な専門とし、一人ひとりの特性を把握し、発達の段階や個人の興味・関心、ライフステージに応じた適切な形でアプローチを行えば、たとえ学びが困難な状況にある人であっても、それが個人の意識を変え、行動にも変化を及ぼす可能性があることについて、実践を通じて体得してきました。この経験は、認知症の人が地域で継続して学んでいく際にも、それ以外の人びとが認知症に関するあらゆる学びに向き合う際にも応用できると考えています。

教育を通じて社会を変えていくには、知識を伝えるだけでなく、その内容・情報量・伝える言葉・伝える順序が対象となる人にとって適切なものか、伝え方は興味・関心を引くものになっているか、またそれを通じて実際に行動を起こせるような動機づけになっているか、といったことを精査していくことが大切です。また伝える対象となる人間一人ひとりの知識や関心、学びに対する姿勢は異なります。こうした意味からは、既存の全国的な認知症の啓発事業においても、より体系的に整理し直していくことが望ましいのではないかと感じています。
教育学を専門にして認知症の啓発活動に取り組んでいる人は、それほど多くはいらっしゃいません。そのため、社会全体で認知症の人を支えるにあたっての、地域を基盤にした適切な学びのあり方は十分に検討されていないのが現状ではないでしょうか。だからこそ、私自身の専門性からこうした取り組みに尽力していくことに意義があると考えています。
創作絵本の制作と出版への想い
私はこれまで、有志市民とともに、認知症の意識啓発活動において、大人向け、子ども向けのプログラムをそれぞれ開発・実施してまいりました。その中で、子ども向けの活動においては、クイズや絵本の読み聞かせ、寸劇等を取り入れながら、認知症について学ぶ機会を提供してきました。

そこで気がついたことの一つとして、認知症に関して様々な症状を伝えるだけでは、偏見や思い込みを植えつけてしまいかねない、ということがありました。重要なことは、認知症の人も私たちと同じように、毎日いろいろな感情が揺れ動いている「同じ人間」だと知ってもらうことです。そのためには、各種の症状を伝えるだけではなく、「認知症の人の気持ち」や「周囲の人の接し方」について、子どもたちにも理解できる世界観の中で、身近な話題を通して分かりやすく伝える必要があります。そこで、こうした想いをよりダイレクトに伝えるには、自身で絵本を創作することが最善だと思い立ちました。
現在、創作絵本の制作は一歩一歩と進んでいます。登場人物のセリフや場面の多くは、実際に私が見聞したリアルな言葉や光景、自身の経験をもとにしています。また、認知症の人にも内容を読んでもらい、違和感がないか確認しました。そのため、この作品にはリアルな言葉があふれています。さらに、私自身が見聞した諸外国における「認知症にやさしい地域づくり」の要素を部分的に取り入れていることも、オリジナルな特徴として挙げられます。
現在、素晴らしい水彩画を描かれる絵本作家であるRoko様により、自身が創作したストーリーに合わせ、イラストの制作を開始していただいています。認知症の人と周囲の人の気持ちや行動が視覚的にも分かりやすく伝わるよう、ステキな登場人物とともに描かれる予定です。同時に、出版社(三恵社様)との話も進めています。絵本のサイズについても、様々な場でご利用いただきやすいように、手に取った際の使いやすさや観客からの見やすさ等にもこだわりました。

絵本の主な登場人物



絵本制作の現段階(但し、絶賛ラフ制作中につき、今後修正があるかもしれません!)
「認知症を正しく理解し、誰もがやさしく支え合える地域をつくる」
そのために、自身の立場からできる一つの貢献の形として、この絵本を多くの人に届け、支え合いの輪を広げたいと考えています。
支援してほしいこと
今回のプロジェクトでは、以下のご支援を希望しています。
第一に、創作した絵本ストーリーの出版を実現し、その活用による啓発活動の質的向上と効果的な展開への支援です。つまり、単に絵本を作るだけではなく、地域のあらゆる人びとが認知症について正しく学び、支え合う社会をつくるためのツールとして活用していただくことにより、広く社会に普及していくことを考えています。そのため、ご支援いただいた資金は、絵本の制作費用に加え、自身の活動の質的向上、より広範な地域への普及・啓発等に活用させていただきます。
第二に、国内外の認知症研究に取り組まれている多様な分野の人びととの効果的な学術交流とその成果還元のための支援です。「認知症にやさしい地域づくり」は、日本だけでなく、60カ国以上の地域で実施されています。したがって、自身が研究者であること、また諸外国の学際的な認知症研究の関係者と交流があること等を活かし、海外の先進事例から得た知見を日本社会に還元していくとともに、日本での経験から得た成果をグローバルな認知症研究や実践にも還元し、双方に利する形で貢献してまいります。

オーストリア・フィラッハの美術館にて行われた、ウィーン応用美術大学教授のR. Mateus-Berr氏他による、アート(ドローイング)を通じた認知症に関する意識啓発ワークショップ時の様子(2024年10月の挑戦者による調査研究にて)
このプロジェクトが成功すれば、より多くの人びとが認知症を正しく理解し、日常の中で認知症の人や困っている人びとに対し、自然に手を差し伸べ、支え合える地域社会の実現に少しずつ近づいていくと思われます。そして、そんな温かい人びとが周囲に増えることが、認知症の人やそのご家族にとっても救いになっていくことでしょう。
支援のお願い
私のプロジェクトでは、自身の専門性を活かし、「認知症にやさしい地域づくり」を推進するため、認知症の人の気持ちや周囲の人の適切な関わり方を分かりやすく伝える創作絵本の出版を予定しています。それを通じて、自身の活動やその元となる調査研究を一層充実させるとともに、賛同してくださる人がこの絵本を活用し、それぞれの地域で活動を広めていってくださることを心から願っています。
出版後は、ご希望がありましたら、私自身が皆様のお近くに出向き、出版予定の絵本の読み聞かせの他、認知症に関する自身の観点からの各種セミナーや相談対応等を提供することも可能です(但し、諸条件がありますので、詳細はリターンの内容をご覧ください)。

すでにわが国では、2022年時点において、認知症の人と軽度認知障がい(予備軍)の人が国民の一千万人以上を占めることが指摘されています(注2)。高齢期に発症する認知症は、年齢とともに発症する人の割合も急増していくため(注5)、高齢化の進展により、今後この割合はさらに高まっていきます。「認知症は特別なことではなく、誰にでも起こりうるもの」と受け止め、正しく知ることにより恐れない気持ちを持つことが必要です。皆さまの温かいご支援を、心よりお願い申し上げます。
※掲載写真は筆者の実際の活動を中心にしたものですが、対象者・実施機関の匿名性担保のため、一部はアート加工をしています。
【注】
1)「認知症にやさしい」とは、英語の“Dementia-friendly”を訳した表現です。
2)二宮利治(2024)「令和5年度老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分)「認知症及び軽度認知症障害の有病率調査並びに将来推計に関する研究」」
3)鈴木尚子・岡 里美(2022)「地域社会に求められる認知症への取り組みに関する一考察 ―徳島県民を対象とした認知症への意識調査から―」徳島大学人と地域共創センター紀要31,33-54(https://www.tokushima-u.ac.jp/fs/3/7/4/9/6/4/_/_____________31_.pdf)
4)佐渡充洋ほか(2015)『わが国における認知症の経済的影響に関する研究―平成26年度総括・分担研究報告書―』(平成26 年度厚生労働科学研究費補助金(認知症対策総合研究事業))
花岡 晋平ほか(2016)「日本における認知症の社会負担―官庁統計を用いた経時分析―」日本医療マネジメント学会雑誌,17(1),pp. 8-13
5)Jorm, A. F. & Jolley, D. (1998). The incidence of dementia: a meta-analysis. Neurology. Sep;51(3):728-33. doi: 10.1212/wnl.51.3.728. PMID: 9748017
国立大学法人徳島大学への寄付と税制について
本プロジェクトへのご寄付は、徳島大学基金「教育・研究・社会貢献事業」への寄付として受入れ、支援に役立てます。徳島大学基金からの謝意としては、広報誌、教育・研究・社会貢献事業報告書をお送りさせていただいております。
国立大学法人徳島大学へのご寄付につきましては、個人からの寄付では所得税の所得控除、住民税(徳島県と県内市町村が条例で指定する寄付金として)の所得控除、法人からの寄付では法人税の損金算入が認められます。
寄付金領収書は本プロジェクト終了日である、2025年5月11日の日付けで発行いたします。税制上の優遇措置をお考えの方は対象となる年にご注意ください。
個人からのご寄付
国立大学法人徳島大学に寄付金を支出した場合は、所得控除制度が適用され、(総所得金額の40%を上限とした寄付金額)から2,000円を差し引いた額が課税所得から控除されます。
実際の税控除額は前記の控除額に各人の税率を乗じたものになります。
個人住民税については、(寄付金(総所得額の30%が限度)-2,000円)×10%が寄付控除額となります。
10%の内訳は、都道府県が指定した寄付金が4%、市町村が指定した寄付金が6%となっています。
確定申告期間に所轄税務署で確定申告手続きを行う必要があります。その際に、国立大学法人徳島大学が発行する『寄付金領収書』が必要になります。
住民税の控除適用のみを受けようとする方は、『寄附金領収書』を添えてお住まいの市町村へ「都道府県民税・市町村民税控除申告」を行ってください。
法人からのご寄付
法人からのご寄付につきましては、寄付金額全額が当該事業年度の損金に算入されます。
この寄付金による損金算入は、国立大学法人徳島大学が発行する『寄附金領収書』で手続きができます。
振込によるご寄附について
このプロジェクトはクレジットカード決済以外に銀行、郵便振込によるご寄附も受け付けています。
入金確認のための支援者様の振込名義などをお知らせいただく必要があります。銀行、郵便振込によるご寄付の場合は必ずご記入をお願いいたします。
≪手順≫
①リターンのコースを選択し、「寄附するボタン」を押してください。
金額を確認し、配送先住所の入力を終えると、振込で支援するかカードで決済するかを選択できます。
表示される画面に従い、次の事項を入力してください。
振込先、口座番号等は申し込みをいただいたのち、支援者様に自動返信メールにて連絡します。
・振込名義人のお名前
・金額
・寄附コースの名称
・領収書などの送付先住所、電話番号、メールアドレス
②ご注意事項
・振込に際しては振込手数料のご負担をお願いいたします。
・カード決済でご利用できるのは、VISA・MASTERのみとなっております。
挑戦者の自己紹介

鈴木尚子
所属:徳島大学 人と地域共創センター
徳島大学 人と地域共創センター 准教授 / 高齢化問題意識啓発グループ代表
専門は教育学(社会教育・生涯学習領域)。乳幼児から高齢者まで幅広い世代の学びを理論的・実証的に研究。海外(豪州・英国)の大学・大学院で、成人教育学についても理論的・実践的に学ぶ。近年は老年学にも関心を寄せる。最終学位: Ph.D. (Continuing Education)
現職では、学生指導の他、公開講座やその他学習プログラム等の企画運営や講師としての関わりを通じて、地域の多様な世代の人びとの学習支援に携わる。また、地域にも出向き、認知症高齢者や障がい者、不登校児等の支援に地域貢献事業として取り組む。認知症については、国内外の先進事例に関する調査研究を行いながら、自治体との連携事業の他、有志市民とともに、独自の意識啓発活動を各地で展開している。
所属学会:日本社会教育学会、日本比較教育学会、日本認知症ケア学会、日本老年社会科学会等


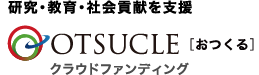















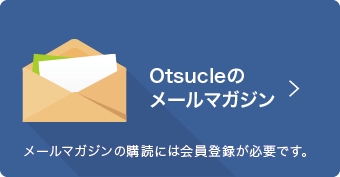
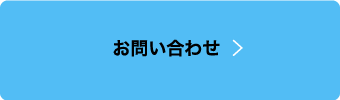
ジュラさん
認知症を持つ方々への偏見がなくなる社会を作れますように、と願っております。絵本はそのためのありがたいツールだと思います。創って下さる事、応援させていただきます。